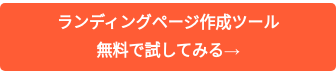- ホーム
- Content Hub
- 無料のランディングページ(LP)作成ツール
- ランディングページとは何か?LPの目的・役割・メリットを徹底解説
ランディングページ(LP)とは、リスティング広告やSNS広告の遷移先となる縦長レイアウトのWebページです。1ページで商品やサービスの特徴、ベネフィットを訴求できるため、ユーザーは情報収集の手間が省け、運営側にとってはスムーズな成約につながります。
ランディングページを初めて作成する方は、まず基礎を理解することが大切です。そこで本記事では、ランディングページの概要や作成するメリット、成果を最大化するための運用ポイントについて解説します。本記事を読むことで、初心者でもランディングページの基礎を一通り身につけられるので、ぜひ最後までご覧ください。
ランディングページ(LP)とは
ランディングページとは、直訳すると「着地するページ」となり、文脈によって広義と狭義の2つの使われ方があります。
広義のランディングページ
広い意味でのランディングページ(Landing page)は、ユーザーがホームページにおいて最初にアクセス(着地)したページのことです。
最初にアクセスしたページがホームページのトップページであれば「トップページ」を、商品ページであればそのページをランディングページとする考え方です。
狭義のランディングページ
狭い意味でのランディングページは、CTA(行動喚起)に特化した広告用Webページを意味します。Webマーケティングではこちらの意味で用いられる場合が多く、本記事でも広告用Webページとしてのランディングページについて解説します。
狭義のランディングページは基本的に1ページで構成され、商品やサービスの特徴や口コミなど、見込み客が必要とする情報が集約されているのが特徴です。バナー広告などを経由してユーザーが最初にアクセスするページがランディングページであると考えるとわかりやすいでしょう。
ランディングページ(LP)とホームページの違い
ランディングページと混同されやすいものにホームページがあります。両者の大きな違いは、対象者と目的、そしてページの構成です。
ランディングページの対象者は、広告をきっかけとして商品・サービスに興味を持ったユーザーです。商品購入や問い合わせなど、「ユーザーの行動を促すこと(コンバージョン)」を目的に作成されるため、ユーザーの注意を逸らさないよう情報を1ページに集約し、他のページへのリンクを極力減らした構成になっています。
一方、ホームページの対象者は、潜在顧客や見込み客以外にも求職者や取引先など、自社に何かしらの関心があるユーザーです。会社概要や採用情報など、複数のページで情報を網羅的に伝えて企業そのものを理解してもらうことがホームページの目的です。そのため、複数の内部リンクを設置するなどしてサイト回遊を促し、より長くサイトに留まってもらう工夫を行います。
このように、ランディングページとホームページではコンセプトが大きく異なります。創業期に「1ページで簡単だから」という理由だけでランディングページを作ると、企業の全体像や信頼性などが伝わりにくくなる可能性があるため注意が必要です。
ランディングページの特徴
ランディングページには、通常のWebサイトとは異なる3つの特徴があります。
- 縦長のレイアウト
- 他ページへ遷移するリンクの少なさ
- 画像がメインコンテンツ
縦長のレイアウト
一般的なランディングページは、縦長のレイアウトで、セールスレターやチラシのようなレイアウトに近いのが特徴です。これはランディングページの役割上、購買意欲の醸成からアクションへとつながる訴求を、1つのページで行う必要があるためです。
営業トークのように、自社商品のメリットやベネフィット、使い方、お客さまの声などを順序立てて紹介し、徐々に見込み客の購買意欲を醸成する仕組みになっています。
他ページへ遷移するリンクの少なさ
ランディングページには、基本的に他ページへのリンクを掲載しないことも特徴です。ランディングページは単独で見込み客のアクションを促す必要があり、他ページに遷移されると本来の目的が達成できなくなるためです。
画像がメインコンテンツ
ランディングページのメインコンテンツは、文章ではなく画像です。画像を用いることで、ユーザーに伝えたい商品の魅力やサービス内容を視覚的かつ直感的に伝えられるためです。文章では表現が難しい商品の使用感やサービスの利用イメージも、写真やイラストを利用すれば端的に伝えられ、ユーザーが理解しやすくなります。
また、CTAボタンの色遣いや配置を目立つように工夫することも、ユーザーにインパクトを与えるための重要な要素です。
ランディングページを作成するメリット
ランディングページは、商品やサービスの訴求に特化した構成になっているため、次のような独自のメリットがあります。
- スムーズに見込み客の購買意欲を高められる
- ターゲットに合わせてクリエイティブのパターンを調整しやすい
- デザインでインパクトを与えられる
スムーズに見込み客の購買意欲を高められる
広告から集客した見込み客を単独で成果に結び付けられるのは、ランディングページならではの特徴です。ファーストビュー・ボディ・クロージングの流れで商品やサービスの特徴、ベネフィットをしっかりと伝えることで、自然に購買意欲を高める効果が期待できます。
また、ページ遷移によるユーザーの離脱を軽減できるため、見込み客の注意を逸らすことなくスムーズにコンバージョンへ導けます。わずか1ページで情報収集から購入までを完結できるため、購買意欲の高い見込み客にとっても大きなメリットです。
ターゲットに合わせてクリエイティブのパターンを調整しやすい
ターゲットに合わせてクリエイティブのパターンを調整できるのも、ランディングページのメリットです。例えば、リスティング広告やSNSなどの流入経路によって、次のようにターゲットの興味の度合いは異なります。
- リスティング広告:商品やサービスに関心がある顕在層
- SNS広告:商品やサービスについて詳しく知らない潜在層
顕在層に向けたランディングページでは、ファーストビューで端的に特徴や導入方法を提示するのが効果的です。一方、潜在層に対しては、問題提起や共感の部分から徐々に商品紹介へ移行した方が良いでしょう。
ランディングページの基本の構成が決まっていれば、構成の順序やレイアウトを変更するだけで広告に合ったクリエイティブに調整できます。流入経路に合わせたランディングページを用意することで、商品やサービスの訴求がターゲットに響きやすくなり、CVR(コンバージョン率)の改善も期待できるでしょう。
デザインでインパクトを与えられる
画像コンテンツを中心に構成されているランディングページは、文字ばかりのページよりもデザイン面で訴求力が高くなります。その結果、ユーザーは商品やサービスの特徴、利用シーンを具体的にイメージしやすくなり、強い印象を与えることができます。
画像コンテンツは情報を簡潔に伝える際にも有効です。複雑な情報やデータを図やイラストで表現する手法はインフォグラフィックと呼ばれ、情報に対するユーザーの理解を深める効果もあります。
ランディングページの作成方法
ランディングページは、「ターゲット設定→構成作成→制作」の流れで作成します。
まずは、ターゲットとなる人物像の年齢層や性別、職業などを設定します。ターゲットを設定することで伝える内容を明確にでき、情報を届けやすくなるためです。
次に、ターゲットに合わせてランディングページの構成を作成します。前述の通り、広告の種類やターゲットが顕在層や潜在層によって効果的な構成は異なるため、コンバージョンにつながる構成を検討しましょう。
最後に、コピーや画像、デザインを制作し、ランディングページに設定すれば完成です。
さらに詳しい作成手順は、こちらの記事で解説しています。
ランディングページ運用のポイント
ここでは、ランディングページを運用するうえでの3つのポイントを解説します。
- Web広告のアクセス数を増やす
- 検証と改善を繰り返す
- 社内で更新できる体制を整える
Web広告のアクセス数を増やす
ランディングページで成果をあげるには、検索エンジンからの自然流入を増やしたり、Web広告を活用したりしてアクセス数を増やすことが欠かせません。
しかし、ランディングページはページ数が1ページに限られ、文章よりも画像を多用し、他のページへのリンクも抑えられるため、高いSEO効果は期待できません。そこで、次のような方法でWeb広告のアクセス数を増やすことが重要です。
- リスティング広告
- SNS広告
- ディスプレイ広告
- チラシやパンフレットのQRコード(二次元バーコード)
- SEOに強いWebサイトからの流入
Web広告自体のアクセス数を増やしてランディングページへの流入を促し、さらにランディングページを最適化すると成果につながりやすくなります。
検証と改善を繰り返す
ランディングページのCVRを高めるにはLPO(ランディングページ最適化)の実施が不可欠であり、成果を検証して継続的に改善を繰り返すことが大切です。
コピーやデザイン、ボタンの文言などを2パターン用意して比較する「A/Bテスト」などを行い、より高いCVRを獲得できるランディングページを目指しましょう。
社内で更新できる体制を整える
ランディングページを更新、改善するスピードは成果に直結するため、社内で簡単に更新できる体制を整えましょう。
例えば、コピーの変更や画像の差し替えが必要になった際に外部の制作会社に都度修正を依頼しなければならない状態では、スピーディーな対応が難しくなってしまいます。また、追加のコストもかかるでしょう。社内で容易に更新できる環境が整っていれば、改善サイクルを速く回すことができ、より高い成果を期待できます。
専門知識に乏しい担当者でも操作しやすいノーコードツールを導入するなど、柔軟な運用体制を構築することが望ましいでしょう。
HubSpotのContent Hubは、無料でランディングページを作成できるノーコードツールです。専門知識は不要でランディングページの作成や更新ができ、効果測定までワンストップで完結するため、ランディングページ運用の内製化におすすめです。
ランディングページ作成時のポイント
ここでは、ランディングページ作成時のポイントを3つ解説します。
- 関連する法令に注意する
- 専用ツールを活用する
- 流入経路ごとにコンテンツを出し分ける
関連する法令に注意する
ランディングページを作成する際は、関連する法令を遵守しなくてはなりません。特に、注意したい法令と内容は以下の通りです。
- 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
- 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
- 特定商取引法(特定商取引に関する法律)
効果・効能を誇張した表現は、景品表示法違反にあたる恐れがあります。また、健康食品や化粧品などを扱う場合には、薬機法により表現が厳しく制限されます。さらに、ECサイトでは販売事業者情報の明示など、特定商取引法への対応も必要です。
ランディングページの運用においてトラブルを未然に防ぎ、信頼を維持するためにも、法令に基づいて適切な情報を掲載することが重要です。
専用ツールを活用する
ランディングページで成果をあげるには、ユーザーの思考の流れに沿った構成作りや魅力的なコピーの考案などのテクニックが必要です。
このようなテクニックを踏まえて効果的にランディングページを作成するには、Webサイトやランディングページを制作するための専用ツールを利用すると良いでしょう。これらのツールにはテンプレートが用意されており、構成やデザインを一から考えることなく標準的なランディングページが作成できるためです。
AI搭載のツールであれば構成やコピーの作成も自動化でき、さらに効率を高められます。
流入経路ごとにコンテンツを出し分ける
出稿する広告によってユーザーの属性やニーズは異なるため、ランディングページごとに構成やデザイン、CTAを調整する必要があります。
例えば、リスティング広告からの流入ではユーザーの課題が顕在化し、購買意欲が高いため、ファーストビューに情報を集中させるなど検索意図の回答となる構成やCTAの配置を意識します。
一方、ユーザーの登録情報(地域・年齢・性別・趣味)を基に広告を配信するSNSでは、商品やサービスの詳細を知らない潜在層がターゲットです。ファーストビューでは問題提起や共感によって興味・関心を引き、徐々に商品紹介へ移行するような、ストーリー性のある構成にすると効果的でしょう。
HubSpotのContent Hubでは、CRM(顧客関係管理)ツールに登録された情報をベースに、ユーザーニーズに合わせてランディングページのコンテンツがパーソナライズされます。
専用ツールを活用して効果的なランディングページを作成しよう
ランディングページは、主にリスティング広告やSNS広告を見て、商品やサービスに興味を持った見込み客の受け皿として利用されます。訪れた見込み客に、購入や問い合わせなど、制作側が狙ったアクションを起こしてもらうことがランディングページの最終的な目的です。
ユーザーのニーズに合わせた構成やCTAの配置を意識して検証と改善を繰り返すことで、ランディングページの効果的な運用につなげていきましょう。
HubSpotのContent Hubは無料プランからお試しいただけるため、ランディングページを作成する予定のある方はお気軽にご利用ください。ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、誰でも簡単にランディングページを作成し、効果測定から改善までワンストップで対応できます。
無料のランディングページ(LP)作成ツール
ウェブデザイナーや開発担当者に頼らなくても、スマホやPCに最適化されたランディングページがすぐに作成可能。
公開後は効果検証しながらリード(見込み客)の創出を促進できます。
この記事をシェアする
ランディングページの関連記事
【基本編】
LPの基礎知識
- ランディングページはなぜ必要?費用対効果などを知る11の統計データ
- ランディングページ(LP)とは?目的や用途についてホームページと比較しながら徹底解説
- ランディングページ(LP)に重要な構成・必要な7つの要素
- 【初心者向け】ランディングページ(LP)作成7つのポイントと基本フロー
- ランディングページ作成の完全ガイド
デザイン・参考サイト
- 【2024年版】おしゃれなランディングページの参考になるギャラリーサイト
- ランディングページの参考にできるデザインまとめサイト9選!探し方のコツも解説
- ランディングページのコンバージョン率を高めるには?デザインにおける7つのコツ
- スマホ向けランディングページ(LP)の重要性と10のコツ&参考ギャラリーサイト
制作ツール・テンプレート
費用・外注関連
【応用編】
LP種類・手法
改善・最適化
- 【参考事例】ランディングページの業種別の作成ポイント8パターン
- 【リスティング広告・SNS広告別】パフォーマンスが高いLPのポイント
- ランディングページ(LP)CVR向上につながる課題ごとの改善方法は?
- LPO(ランディングページ最適化)とは?CV率を改善する基本4ステップ&7つのツール
HubSpot日本語ブログでは、世界中のHubSpotの知見を活かし、日本のビジネスパーソンの課題解決に繋がるような情報を提供しています。詳しくはHubSpotブログをご覧ください。